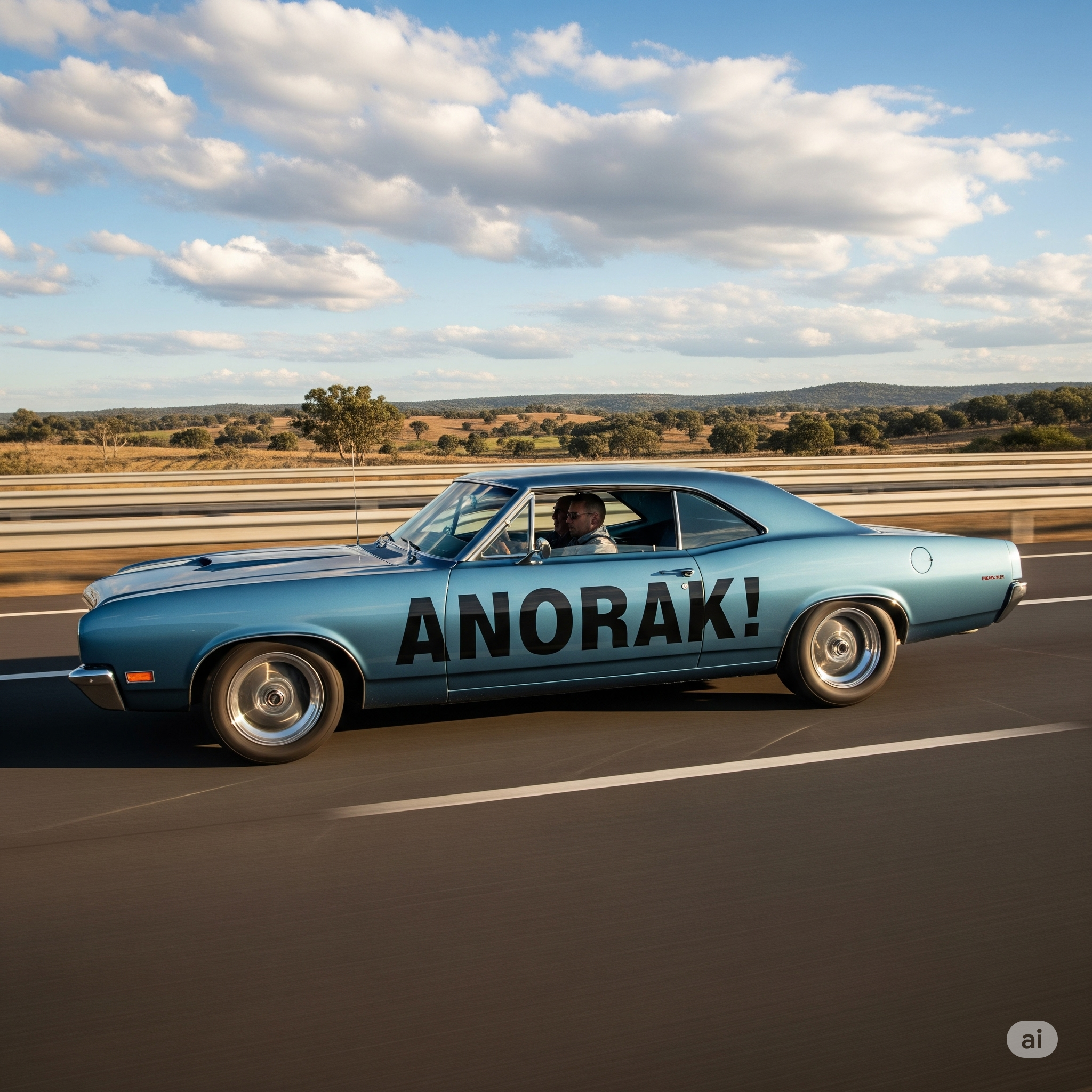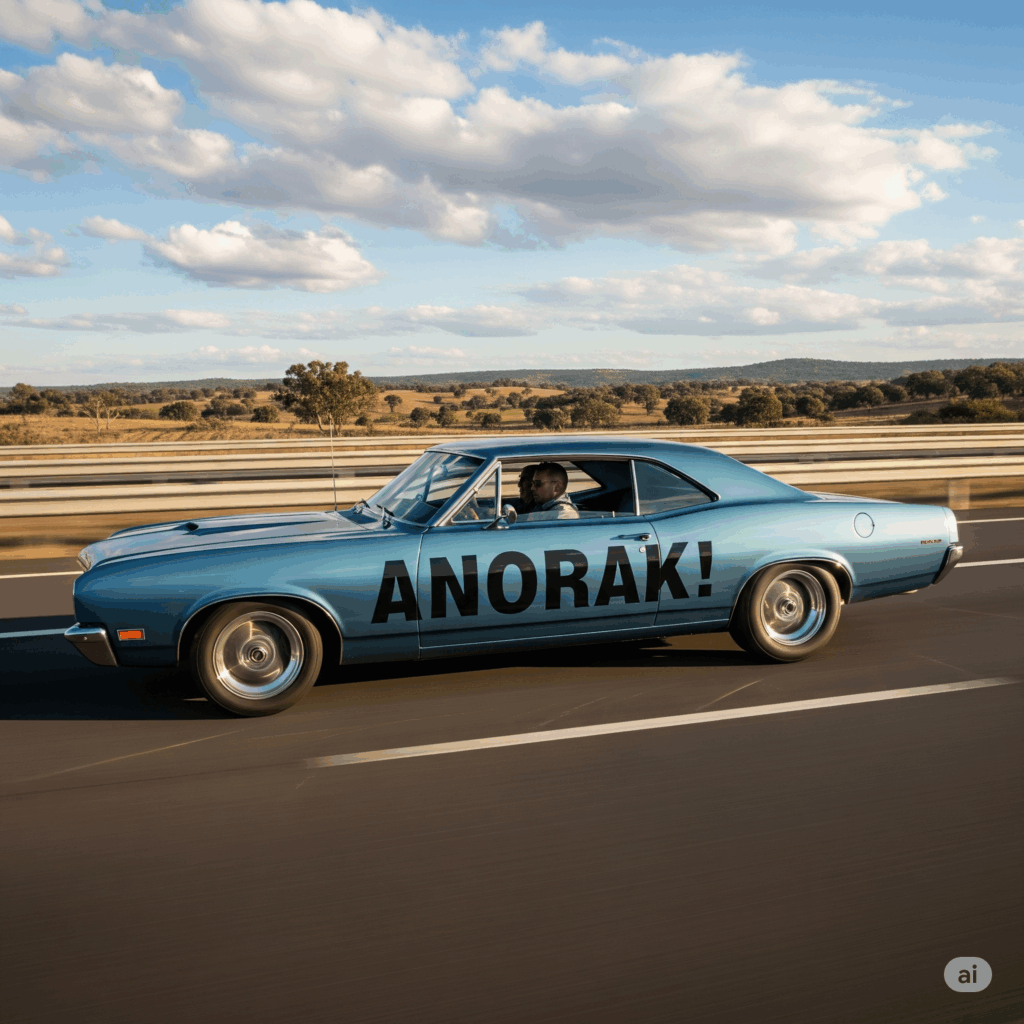
2025年6月7日、東京を拠点に活動するオルタナティヴ・ロックバンド、ANORAK!がニューシングル『Shade』を配信リリースした 1。この楽曲は、昨年『FUJI ROCK FESTIVAL ’24』ROOKIE A GO-GOへの出演を果たし、2ndアルバム『Self-actualization and the ignorance and hesitation towards it』で国内外のツアーを成功させた彼らが放つ、キャリアの新たな一歩を象徴する重要な一曲である 2。本稿では、この『Shade』という楽曲が内包する多層的な魅力を、その革新的なサウンド、内省的な歌詞、そして映像表現から総合的に解き明かし、ANORAK!が現在どのような音楽的境地に立っているのかを詳細に分析していく。
このシングルのリリースは、単なる新曲発表という枠を超えた、バンドからの戦略的な「声明」とも解釈できる。なぜなら、リリース日(2025年6月7日)は、彼らにとってキャリア最大規模となる渋谷CLUB QUATTROでのツアーファイナルワンマンライブ(6月11日)の直前という、極めて意図的なタイミングであったからだ 3。これは、過去の集大成と未来への展望を同時に提示することで、リスナーの期待感を最大限に高めるための布石であり、バンドがこの新曲に込めた自信の表れに他ならない。
音楽的革新性:ミッドウェストエモとダンスミュージックの交錯
1.1. 破壊と再構築:ジャンルを越境するサウンド
『Shade』のサウンドを特徴づける上で、まず注目すべきは、そのジャンルを横断する革新性である。楽曲のミュージックビデオ(以下、MV)の概要欄には、「#electronicpop」「#dancemusic」「#midwestemomusic」という、一見すると相反する複数のハッシュタグが付されている 4。これは、ANORAK!の音楽的ルーツと、現在進行形の音楽的志向が巧みに融合していることを示している。
Ototoyの記事が「ダンス・ミュージックへと接近したアルバムの路線をさらに押し進めるような1曲」と指摘しているように、『Shade』は前作アルバム『Self-actualization and the ignorance and hesitation towards it』で顕著になった、強烈なエレクトロニックサウンドへの変化をさらに深化させた作品である 3。彼らは2010年代に世界で巻き起こったエモリバイバルに触発されて結成されたバンドであり、その初期の音楽性はエモやメロディックパンク、インディーロックの文脈で語られてきた 6。しかし、彼らのサウンドは単なる懐古趣味に留まらない。
この新しいサウンドの地平を開く上で重要な役割を担っているのが、卓越した演奏技術と構成力である。後藤正文(ASIAN KUNG-FU GENERATION)が彼らのギターサウンドに「USっぽさ」を感じ、ポストロックやマスロックの要素を指摘したように、メロディアスでテクニカルなギターフレーズは健在である 8。さらに、mabanuaが「地味にテクニカルなことをやる」と評したドラムが、この新しいダンスミュージック路線を支える強固なリズムの土台を築いている 8。アメリカのバンドがガレージで練習する文化があるためドラムが上手いバンドが多い、という後藤の分析にもあるように、ANORAK!のドラムは単なるビートキーピングを超え、エレクトロニックな要素と融合する複雑なグルーヴを生み出している 8。
これらの要素が組み合わさることで、ANORAK!はルーツであるエモの持つ感情的な疾走感を、より現代的で洗練された表現へと昇華させている。これは単なる実験ではなく、ANORAK!の音楽を現代的に「再定義」する試みである。
1.2. 批評家たちが認めた「普遍性と先進性」
ANORAK!の音楽性は、日本の音楽シーンを牽引する著名な音楽家や批評家たちからも高い評価を受けている。ASIAN KUNG-FU GENERATIONの後藤正文、チャットモンチー済のaccobin、ドラマーのmabanua、音楽雑誌『MUSICA』編集長の有泉智子といった面々が、彼らの1stアルバム『ANORAK!』について詳細なレビューを寄せていた 8。
後藤正文は、彼らのサウンドにアメリカン・フットボールやミネラルといったUSエモのルーツを見出しつつも、「過剰なコスプレ感」や「チープな方が偉い」といった自意識がない点を高く評価している 8。また、accobinも、90年代末から2000年代初頭のバンドサウンドの文脈を感じさせつつも、「音像が細分化されている現代において、むしろ際立つサウンド」と評し、その音作りの「潔さ」を称賛した 8。
これらの批評は、ANORAK!が単なる「エモバンド」に留まらない、シーン全体を牽引する存在になりつつあることの証明である。過去のジャンルをただ模倣するのではなく、独自の解釈で「今」の音楽を創造しているという評価は、彼らが自信を持って『Shade』のようなアグレッシブな路線変更を押し進めることができた心理的背景となっていると考えられる。彼らは、過去の成功に安住することなく、常にアーティストとして進化し続ける姿勢を貫いている。
言葉の「Shade」に潜む二重性:デジタルとリアルの狭間で
2.1. 英語詩と日本語詩が描く内面の葛藤
『Shade』の歌詞は、英語と日本語が織り交ぜられ、複雑な内面の葛藤を描き出している 9。この二つの言語が果たす役割を詳細に読み解くことで、楽曲の核心に迫ることができる。
楽曲の英語詞は、普遍的かつ現代的なテーマを扱っている。「Wipe the cache and I won’t crash under the weight of my thoughts, caught in hate-fueled knots」(キャッシュを削除して、もう自己嫌悪に絡まるような考えに押し潰されることもない)というフレーズは、デジタル社会における内省のメタファーと捉えられる 4。また、「Just to flash around, I shrink without a sound」(自分をよく見せるために、音もなく矮小になっていく)という表現は、SNSなどで見せかけの自己を演出し、その代償として内面的な自己がすり減っていく現代的なアイデンティティの危機を象徴している 4。
一方、日本語詞は、より個人的で具体的な「場所」や「関係性」における苦悩を吐露している。「不慣れなのはこの場所にね 他じゃ居れない」(この場所には慣れないけれど、他にはいられない)という矛盾した感情は、特定のコミュニティや人間関係、ひいては自分自身の内面に帰属する葛藤を示唆している 9。これは、デジタルとリアルの狭間で揺れ動き、居場所を求めながらも、その場所に馴染めないでいる現代人の「影」の部分を鮮やかに描き出している。
2.2. タイトル『Shade』が持つ多義的な意味
楽曲のタイトルである『Shade』は、単なる「影」という言葉以上の多義性を持っている。これは、自己の内面に潜む「陰影」、他者や社会に対して見せる「影武者」のような自己、さらには、主流ではない音楽シーンにおける「日陰者」としてのアイデンティティをも示唆している可能性がある。
前作でエレクトロニックなサウンドに接近し、今作でさらにダンスミュージックへと舵を切る中で、ANORAK!はルーツであるエモという「影」を抱えながら、新たな光を掴もうとしている。この挑戦には、エモファンから離れてしまうのではないかという不安や、新しいサウンドが市場に受け入れられるかという葛藤も伴うだろう。内省的な歌詞は、そうしたアーティストとしての誠実さと、市場における立ち位置のバランスを取ろうとする彼らの姿を映し出している。
映像が描く『Shade』の視覚的解釈
『Shade』のMVは、楽曲の持つ新たな音楽性を視覚的に増幅させる役割を担っている。MVの監督は、映像作家の田辺泰隆氏が務めている 4。なお、プロ野球や高校野球の関係者として知られる同名の人物とは別人である 11。
提供資料にはMVの具体的な映像内容についての記述はないが、MVのタグが示すように、楽曲が持つエレクトロニックな要素やダンスミュージックの疾走感を視覚的に表現する演出が随所に散りばめられていると推察される 4。例えば、タイトな編集、電子的なビートを想起させる光の演出、そして内省的な歌詞を象徴するメンバーの表情や動きなど、音楽と映像が密接に共鳴することで、楽曲の世界観はより深く、力強く表現されている。MVを視聴することで、楽曲だけでは捉えきれない『Shade』の総合芸術としての魅力を感じ取ることができるだろう。
ANORAK!の軌跡と『Shade』が指し示す未来
ANORAK!のこれまでの歩みを振り返ることで、『Shade』という楽曲が彼らのキャリアにおいてどのような位置づけにあるのかが明確になる。以下の年表は、彼らの主要な作品と出来事をまとめたものである。
ANORAK! 主要作品・イベント年表
| 年 | 作品・イベント名 | ジャンル的特徴(概説) | 備考 |
| 2019年 | 結成 | Emo/Punkサウンド | Gt/Voの前田を中心に結成。2010年代のエモリバイバルに触発される 6。 |
| 2020年 | 1st EP『I’m Getting Bored of This Party』 | Emo/Punk | バンド活動の初期作品。 |
| 2022年 | 1st Full Album『ANORAK!』 | Emo/Punkサウンド | 後藤正文らが普遍性と革新性を高く評価 8。 |
| 2024年 | 2nd Album『Self-actualization and the ignorance and hesitation towards it』 | Electronic/Dance Musicへの接近 | アジア6カ国9公演、アメリカツアー14公演を完遂。フジロックに出演 2。 |
| 2025年 | シングル『Shade』 | EmoとElectronic/Dance Musicの融合 | 2ndアルバムの路線をさらに押し進めた一曲 1。 |
| 2025年 | 渋谷CLUB QUATTRO ワンマンライブ | キャリア最大規模のライブ | リリース直後の集大成ライブ 3。 |
この年表が示すように、ANORAK!は単なる一過性のトレンドに終わらない、着実なキャリアを歩んできた。エモリバイバルをルーツに持ちながらも、2ndアルバムで大胆なジャンルの拡張に挑戦し、国内外でのツアーを成功させたことは、彼らが一時的なブームではなく、日本のオルタナティヴロックシーンにおける重要なプレイヤーへと成長していることを物語る。
そして、『Shade』は、その進化の最前線に位置する楽曲である。過去のルーツへの敬意と、未来への大胆な挑戦を両立させたこの曲は、ANORAK!が今後、より広く多様なリスナーを獲得するための「呼び水」となる可能性を秘めている。ダンスミュージックの要素を取り入れたことで、コアなエモファン以外にもアピールする扉を開いたのだ。今後の国内ツアー(『Fav Riff Tour 2025』)や、様々なイベントへの出演(FUTURE WAVE、WWW presents DialHouseなど)で、この新しいサウンドがどのように昇華されるのか、バンドの活動から目が離せない 14。ANORAK!は『Shade』を通じて、自らの音楽的「Shade」(影)を乗り越え、新たな光を掴もうとしているのである。
結び
『Shade』は、ANORAK!がこれまでの成功に安住することなく、常に挑戦と進化を続けるバンドであることを証明する力作である。ミッドウェストエモの疾走感と、エレクトロニックなダンスミュージックのグルーヴが融合したサウンドは、彼らの音楽的探求心の深さを示す。そして、デジタルとリアルの狭間で揺れる現代人の内面を映し出した歌詞は、多くのリスナーの共感を呼ぶだろう。
このコラムを通じて、読者がANORAK!の音楽の奥深さを再認識し、MVを改めて視聴するきっかけとなれば幸いである。なお、本稿ではバンド「ANORAK!」の楽曲について論じており、アウトドアブランド「アノラック」や、同名のアイドルグループ「AnoraK」に関する情報は本件とは無関係であるため、意図的に除外した 15。ANORAK!の挑戦はまだ始まったばかりだ。彼らのライブに足を運び、その生の熱量を体感することで、新たな音楽体験が待っているに違いない。